自己啓発の分野でベストセラーになっている本が何冊かあります。例えば、スティーブン・コヴィーの「7つの習慣」やデール・カーネギーの「人を動かす」等です。
これらの本を読んで感銘を受けた方は結構いるのではないかと。僕もその一人です。いいこと書いてありますよね。
一方で行動科学を学ぶと、こういった本の内容から一歩距離を置くようになってしまいます。循環理論に陥っている可能性を危惧するからでしょうか。
ただそこで得られる学びが全て無駄だというわけではありません。人生のある局面において、非常に有効に働くこともしばしばあります。
そうすると気になるのが、こういった本から得た所謂「生き方の原則」みたいなものは、持続的な幸福と成功を得るのにどう役立つのかという点です。
以下、これについて考察します。
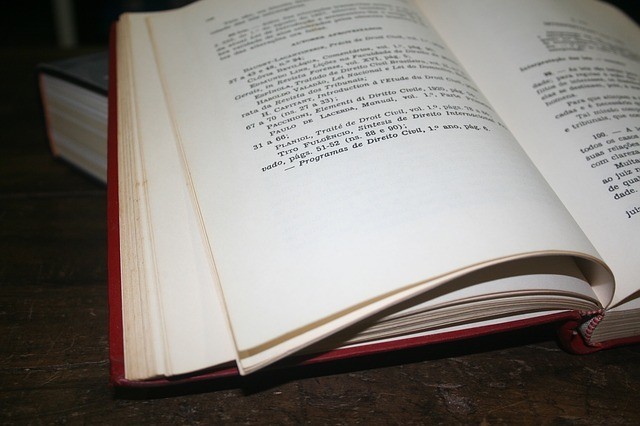
”生き方の原則”は本当に有効なのだろうか
スティーブン・コヴィーの「7つの習慣」やデール・カーネギーの「人を動かす」といった書籍を読んだことはあるでしょうか。あるいはこれらに類する他の書籍でもいいです。
こういった本には「生き方の原則」が記述されています。
僕にとってこういったものの中で、最も印象に残っているのは次の本で学びました。

- 作者: アービンジャーインスティチュート,金森重樹,冨永星
- 出版社/メーカー: 大和書房
- 発売日: 2006/10/19
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 156人 クリック: 3,495回
- この商品を含むブログ (418件) を見る
この本によれば、自己を正当化し他人を責めるかぎり、その人間関係は不健全で敵対的なものになり、悪化の一途を辿ってしまうとのこと。その悪循環から抜け出すきっかけとなるかもしれないものが、次の問いかけです。
もしかしたら間違っているのは自分かもしれない
この問いかけは人間関係で困難を抱えた時に、何度もヒントをくれました。
あるいは7つの習慣からピックアップするならば「インサイド・アウトの原則」も有名でしょうか。僕たちは公的成功を求めて様々なノウハウを学ぼうとするが、先に私的成功を成し遂げなければ公的成功は得られないといったものです。
常にインサイド・アウトであることが、持続的な幸福と成功に欠かせないという話。
こういった「生き方の原則」は何やら僕たちに重要にことを示唆しているように思えますし、これに従って生きることができればより良い人生が送れそうにも思えます。
しかし、それは本当なのでしょうか。この点を考察していきます。
”考え方”は人生にどう影響するのか
言葉は行動に対して3つの機能を持つ
生き方の原則は、それを学ぶ段階において「言語」の形をとります。また生き方の原則が実際に人生に影響するためには、それがどこかで僕たちの行動を変える必要があります。
言葉の影響の与え方は大まかに3つです。
- 適切な行動についてのヒントを与える
- 行動または行動の結果の価値を変容する
- どのように行動すべきかを指示する
例えば「もしかしたら間違っているのは自分かもしれない」という問いかけは、次に相手に投げかける言葉についてのヒントをくれることになるかもしれませんし、相手の反応についての意味を変化させるかもしれません。
生き方の原則の内容ではなく、どう機能するかに注目しよう
そしてそれが健全な人間関係の形成に有効に働いたとしたら、生き方の原則が機能した場面といえるでしょう。でも、もしかしたら生き方の原則が機能しない場面もあるのかもしれません。
ただ、いずれにせよ注目すべきなのは「機能」にあります。
つまり「生き方の原則」はその内容そのものによって評価するのではなく、それがどのような役割を果たそうとしているのかどうかで評価すべきなのです。このような物事の見方・捉え方を機能的文脈主義といいます。道具主義といってもいいでしょうか。
機能的文脈主義からみた生き方の原則の持つ役割
生き方の原則が有効に機能しない場面もある
さて、では機能的文脈主義の立場から生き方の原則をみていきましょう。
考えてみたいのは僕に平和で健全な人間関係をもたらしてくれた言葉である「もしかしたら間違っているのは自分かもしれない」という問いかけについて。この問いかけが有効に機能しない場面は想定できるでしょうか。
僕は次のように考えます。
もしいまこの瞬間、相手からもたらされるものが破壊的かつ緊急性の高い言葉や暴力であったとしたら、この問いかけは上手く機能しないだろう。
このような場面において優先すべきは身の安全です。もしかしたら自分が間違っているのかもしれないといった問いかけは、安全を確保するのにマイナスにすら働く可能性があります。そんなことは安全を確保できてから考えればいいのです。
あるいは自分を責めがちな人にとっても、あまり有効には機能しないかもしれません。他にも「他者を責めがちな相手」を責めるために、この言葉を利用してしまう人がいるかもしれません。
あらゆる生き方の原則は、それを用いる状況とセットで評価すべきである
これらはこの問いかけの本来の意図から大きく逸脱してしまっていますが、生き方の原則がおかれた場面次第では、誤って機能してしまうことは十分に考えられます。
つまりあらゆる生き方の原則は、それがおかれた場面(文脈)において、持続的な幸福と成功に貢献するよう機能しているかどうかをチェックすべきなのです。
もしかしたら普遍的に機能する原則もあるのかもしれません。7つの習慣にある「主体的である」などは多くの場面で役に立つ考え方だろうと思います。
ただいずれせよ、全ての原則は常に機能すると盲目的に信じてはいけません。それがいまの自分にどのように機能するのか。その視点をもって扱うといいでしょう。
まとめ
本記事でお伝えしたのは次の3点です。
- 生き方の原則は人生のある局面において、有効に機能することがある。
- 生き方の原則が有効に機能するかどうかは、それを用いようとする状況(文脈)に依存する。原則はその内容によって評価するのではなく、機能に注目して評価すべきである。
- どのような原則であろうとも、全ての状況で正しいと盲目的に信じてはいけない。それがいまの状況において、持続的な幸福と成功に貢献するものかどうかを見極めなければならない。